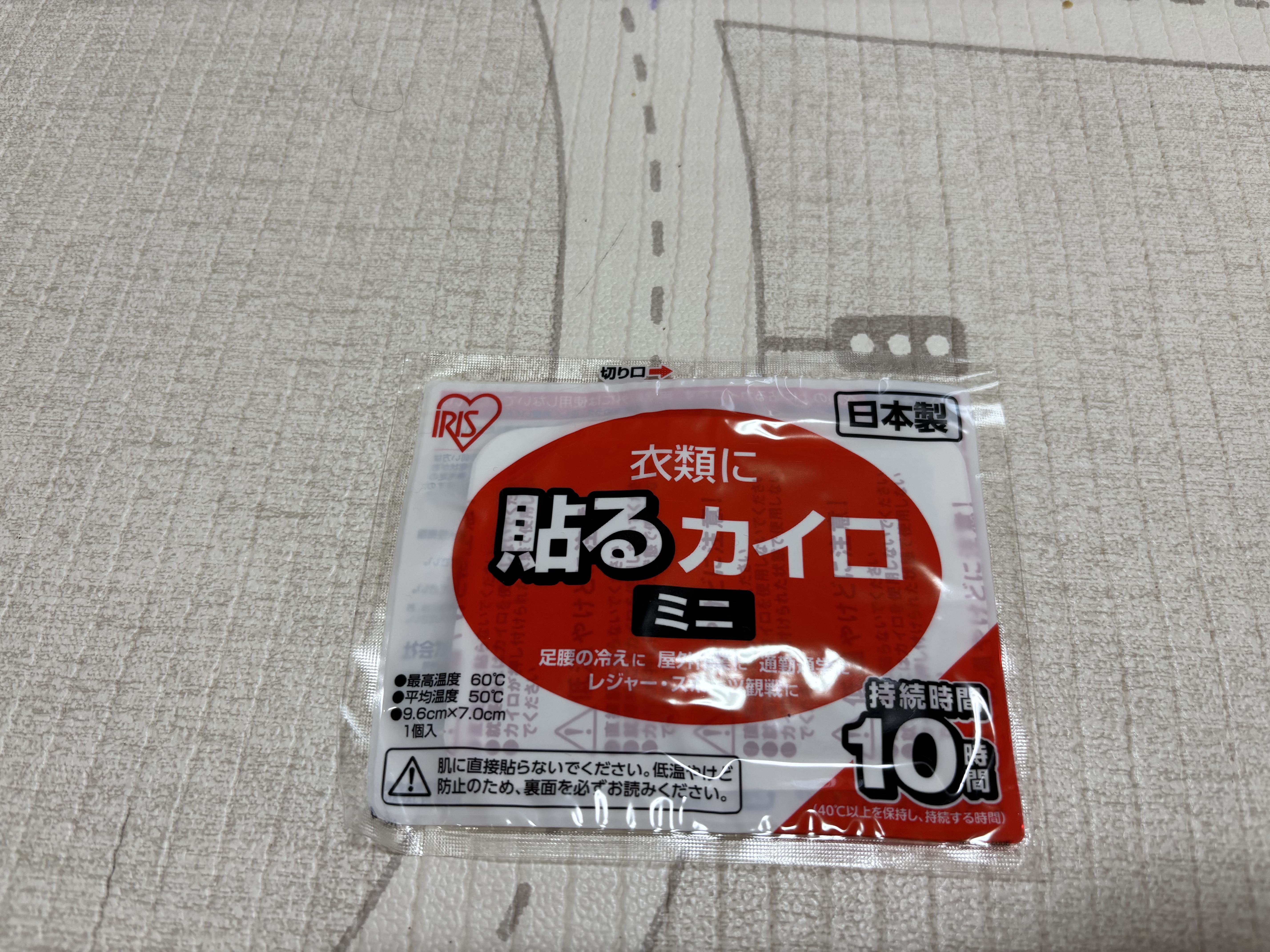「理想と現実」釣具店員さんになりたい人に知っておいて欲しいこと「元釣具屋の暴露」

※アイキャッチ画像はイメージです。
僕は元々、某有名釣具チェーンの釣具店員をしていました。
そして、長い間勤め、最終的には店長を経験させてもらい、釣具関係のお仕事の裏側や店舗の実態について非常によく勉強させていただきました。
本当に何十年と経験しているベテランの方からすれば、僕が釣具店のことを語るのは少しおこがましいかなぁと思い、記事にはしないつもりでしたが、どうしてもこの記事を必要としてくれる人がいると感じてしまい、勢いで記事を書き始めました。笑
僕が最も辛かったのは釣りが好きでしょうがないが故の「理想と現実」のギャップでした。
釣具店は個人店であれば、また違う角度の話があるのかもしれませんが、チェーン店の釣具屋の本質は小売店です。
つまり、ビジネスとして利潤を追求しており、釣具店がやりたいからやっているというより、釣具という商材で利益を出すために運営されています。
そのため、極端なことを言えば、釣具店が本当に欲しいものはお客様を喜ばすことではなく「粗利」なのです。
もちろん店員さんはお客様に喜んでもらうために働いている人も多くいらっしゃいます。
ですが、会社から「お客様を喜ばせなさい」という指示はなく、単純に数字の話や他店との比較、そしていかに粗利を増やすかという無機質な部分のコミュニケーションしかありませんでした。
店長や責任のある立場の仕事をしている方であれば、会社からの「売り上げを上げ、粗利を増やせ」というプレッシャーしかありません。
そんな経験のある僕だからこそ、お話ができると思っています。
釣具店の理想と現実について今回は詳しくお話しします。
もちろん、楽しく釣具店で働いている人も沢山みていますし、決してネガティブなイメージだけをお伝えしたい訳ではありませんが、実態について、特にこれから釣り関係の仕事につきたいと考えている若い人にとって知っておかないといけなと内容だと思い、記事を執筆しています。
僕が釣具店を辞めた理由
まず、僕が釣具店を辞めた大きな理由について説明させてください。
もちろん、某チェーン店の釣具店に入社し、本社の上司、下積み時代を支えてくれた当時の店長や上司、諸先輩方には心から感謝しております。
今は違う仕事をしていますが、釣具店の時の業務のやり方や優先順位の仕方など、今に大いに役立つことは間違いなく、この釣具店時代に学んだことです。
そのため、今となっては感謝の気持ちでいっぱいです。
それだけは忘れたくないです。
ただ、当時の自分の思いは事実として伝えたいので、これからお話しします。
- 結局、数字しか見られていない
- 「仕事も釣り・趣味も釣り」ギャップが大きすぎた
- 自分の店舗が監獄に思えたあの日・・・
店長時代、とても優秀なアルバイトの後輩達に僕は支えられていました。
何をするにもテキパキやり、僕がお客様と談笑している時も隣で商品を陳列し、レジ打ちを行い、商品が不足したことを報告してくれたり、上司の僕としては申し分ありませんでした。
そのアルバイトの子は、将来的にこの会社の正社員になりたいという気持ちで働いてくれていたようです。
ですが、ある時、僕は本社の意向を聞いて「耳を疑いました」
「このままだと人件費が嵩むからそのアルバイトの子を正社員にするつもりはない」ということでした。
「しかし、本人のやる気を削がないように正社員の話はし続けろ」という指示でした。
つまり、正社員になりたいアルバイトの子にはこうしたら正社員になれるかもしれないという話をする一方、なれない正社員の夢を見させ続ける飼い殺しの状態にせざるを得なかったのです。
このことがきっかけで、僕は心が会社から離れていきました。
これは数字しか見えていない人からの物の見方です。
僕個人の力がなく、本社への推薦の力が足りなかったことはもちろんあります。
しかし、根本的に働いてくれる人を「数字」としてしか判断していない現状が嫌でしょうがなかったのです。
また、釣具店は釣具を中心としてアウトドア系のアイテムを販売することが目的です。
そのため、売れる商品を仕入れる必要があります。
コーナー毎に担当者を振り分け、商材を仕入させることもありますが、個人がおすすめしている商品は、上司や本社からストップが入り、自分が本当におすすめできる商品を仕入れ出来なかったりします。
売れる商品と自分が好きな商品は違います。
多くの釣具店員はこのギャップに苦しむと思います。
理由はお客様に真の意味で情熱を持って提案・推奨できるかと言えば、そうではないからです。
僕は人一倍、製品にこだわりが強いタイプですので、個人店やセレクトショップ向きの人間なんだと今になって思います。笑
また、大好きな釣りのことを中心に仕事ができると思えば、大間違いで日々の店舗運営の雑務・業務に追われます。
その隙間をぬって、店舗の仕入れや在庫管理、シフト管理、そして、本社への報告業務などやることは盛り沢山です。
釣りのことが好きで、釣具のことをじっくり考えるなんて余裕はありません。
そして、何より連日のように他店などとの比較と競争を煽られます。
この勉強成績のように「比較と競争」が嫌いな人は釣具店という物を売る小売店ではうまくいかないような気がします。
どこまで言っても、何々店の何々さんはこういう実績を立てた、とか、何々店は今季の売り上げがすごい、みたいな比較が連日のようにされます。
釣具や釣りが好きで入社したのに、やっていることは企業が欲しい粗利を出すために他人と競争することでした。
これを働きながら理解するのに、結構時間がかかりました。
「そんなことはない!釣具店員はお客様のことを考えてポップ作りや製品の並び方や店舗の清掃などしっかりやっている!」という声もありそうですが、そうではないのです。
本社より求められることの本質を突き詰めれば「粗利を出すために競争しろ」と求められるです。
厳しいようですが、全国のチェーン店系の店舗のある程度の責任者であれば、必ず求められると思います。
そこでもらっている給料を考えた時、ただ釣りが好きで釣りのことを語りたいだけだった僕にとって精神的な負荷が大きすぎると感じ始めたのです。
僕の場合はですよ?笑
そして、仕事でも釣り、趣味でも釣りということになり、お腹がいっぱいになってしまう感覚になってしまいました。
その時に感じたのは、釣りを楽しむためには釣りから離れることも必要なのでは?ということでした。
実際、その時の本社系の上司は釣りを楽しんでやっているという人は少ない印象でした。
むしろ、アルバイトスタッフや店舗スタッフの方が釣りをやっている数は多い傾向にあります。
出世すればするほど、釣りから離れていくのです。笑
最終的に多分働きすぎで、毎朝、電車に乗って店舗に向かう足がだんだん重くなり、精神的にも辛くなり、やる気がなくなっていきます。
朝から夜中までずっと店舗にいて、こうしたいけど、色々自分が思うように出来ないという葛藤とこのまま店舗勤めのまま人生を終えたらどうしようという思いが錯綜して、結果的に店舗が開かれた刑務所のように思えてきました。
相当鬱っぽいですよね。笑
その時代は確か1日1食で、夜中に米を2合どか食いしていましたね。
朝と昼は忙しくて食べられないので。
(僕の場合ちょっと特殊にブラック過ぎたかもしれません。今の釣具店はまずそんなことないと思います。)
そんなこんなで、辞めることを思い当たり、すぐに転職エージェントに会いに行き、1ヶ月後には退職することになったのです。
最後、お世話になった上司に話をする時、その上司の反応はとても意外でした。
激怒されるか、強い引き留めにあるかと心配でしたが、言われたのは「お前よく次の仕事見つけて辞めたな」というまさかの褒め言葉でした。
内心、上司も寂しかったと思います。
ですが、止めても意味がないと理解していた上司はそう言ったのではないでしょうか。
最後はスッキリ退職し、人生の歩みを進めたのは今でもよく覚えています。
また、各チェーン店で給料は違うのはもちろんですが、このご時世ですし、給料は相当あがりにくい職種だと思います。
人が最も輝く瞬間
釣具店員をやっていて、自分自身最も輝いているなぁと感じたことはお客様に「自分の得意な釣りの説明」をしている時です。
自分が好きなことを仕事で語れるのですから、こんな幸せなことはありません。
中には僕の話を元に魚が釣れて、また来店される方もいます。
そして、リピーターになり、日々そうした方のお話を聞く立場に替わっていくのです。
そういう釣りが好きになるプロセス、釣りを語る楽しみがある点はこの仕事で最も醍醐味のある部分だと思います。
お客様に何か質問を受ける時は、大体が何か探している時か釣りのことがわからないので教えて欲しい時です。
店員さんはお客様のご予算の感覚と何を求めているのか、何を目的に釣りをするのか、色々ヒアリングが必要です。
実は思った以上に、コミュニケーション能力が試される仕事でもあります。
一方的な店員語りでは、お客様が不満です。
お客様が自身のことを話したらじっと聞くことも、次の販売やコミュニケーションに繋がることです。
そして、お客様が釣りの自慢をし始めたら、思いっきり驚いて、話を伺うと大体の人が満足して帰られます。
そういう人が増えれば、お店のファンが増えていくのです。
という経験的な成功面は知っているのですが、実際は自分の機嫌によってお客様への対応が変わったり、他のことで忙しくて会話が出来ないということも多々ありました。
ですので、理想と現実のギャップに悩むのです。
本当はお客様とじっくり話がしたいのですが、そう出来ない状況であることも少なくないのがチェーン店の抱える大きな問題でもあると感じています。
僕が完全独立して釣具店を運営するなら、「スタッフ全員が気持ちよく、機嫌よく働ける環境を整えて、あえてお店には遊びの雰囲気を漂わせます」
釣具店に来るお客様は、釣具を見ているようで、色々なことを考えています。
この釣具があったら、どこに釣りに行こうとか、この道具が自分のケースに入るかなぁとか、色々なことを楽しく考える場でもあります。
ですので、より遊びの雰囲気が漂っていた方が、なぜかお客様も楽しく、スタッフも元気に働けるという好循環がうまれると思っています。
釣りは楽しいものです。
楽しい雰囲気をお店が出す点は、他の小売店にはなかなか真似が出来ない釣りならではの強みだと思います。
釣具店のスタッフこそ、人生そのものを楽しむマインドが大事だと常々感じます。
関東の某釣具店は色々回りますが、店員が不機嫌な顔をしていたり、辛そうにしていたり、逆に退屈そうにしている場所には、そういう楽しい雰囲気のお客様は寄り付かなくなり、売り上げも落ちていきます。
僕は釣具店のお店作りの最大の肝はその「雰囲気作り」だと信じてやみません。
その理想に近づけられなかったのは、現役時代、自分自身が満足のいく働き方や生き方が出来ていなかったことに他なりません。
今となってはそう考えています。
また、釣具店の経営陣は、数字のみで語るのではなく、お店とは日々変化する生き物であること、そして、お店の雰囲気はいつもいるスタッフさんが作っていることをしっかり理解する必要があると思っています。
全ての本質は「人」なのです。
人がいなければ何も出来ないのです。
スタッフも釣人も「楽しく、元気に」過ごせるようになれると良いですね。
釣具店の本当の価値
ネットに蔓延る多くの方の意見に今はネットで何でも揃えるから店舗はいらないという意見もよく耳にします。
実際、ECサイト業界も伸びていますし、釣り業界には、釣り場がどんどん禁止になる問題、沖堤防に渡れなくなった、高齢化で釣船の廃業、さらには熊の増加被害など、逆風が吹き荒れています。
しかし、実の釣具店の価値は消えることはないと思っています。
その価値の本質とは何か。
それは「考える場所」を提供していることと「人と人との繋がり」に他なりません。
ある程度、釣りをしている人ならふらっと休日によった釣具店でついつい長居してしまった経験は多くあると思います。
なぜ、長居するのかと言えば、釣具を眺めながら色々考えたりしているからです。
人によっては色々なアイディアが浮かんで次の釣行時の妄想で頭がいっぱいになることさえあります。
単純に色々な商品を眺めているだけでも楽しいという側面もあります。
実物の商品を比べたりしているだけで、色々なアイディアが浮かんできたりしますよね。
これらは店舗側の努力や工夫があってはじめてお客様のそうした時間を創造できるのですが、釣具店にはネットにはないそうした魅力があります。
ネット販売は事前に知っている商品をメインに購入しますが、色々思考したり、実物を見ながら釣行時の妄想を膨らませることは難しいのです。
釣具店でしか深い体験は出来ないのです。
特に大型店舗は半日でも入れそうな気がします。笑
それに全てネットで購入できるというのは嘘です。
実店舗でないと卸せないアイテムはまだまだ無数にあります。
そして、何よりも大きな価値は小さな地方の釣具店の価値にもつながるのですが、その釣具店にいつもいる店員さんと仲良くなれることです。
店員さんからスペシャルな情報を聞いたり、日々のコミュニケーションの中で自分の釣り人生の満足感が高くなることも少なくありません。
ネットでいくらSNSで呟いても、メッセージで会話をしても、実際に対面で好きな釣りの話をする満足感には叶わないのです。
これこそが時代の変化に流されない普遍的な価値であると思っています。
釣具店の店員さんから教えてもらった情報を元に実際に釣りに行ったり、コミュニケーションが人間の行動を促しているのです。
実際、釣具店員時代、とても難しい小型店舗で売り上げをぐんぐん伸ばす店長の隣で働いたことがありましたが、日々の業務は他スタッフに任せ、店長はお客様との会話を中心に仕事をしているという状態で、しかも、次から次へと店長と会話したい人が来店される状態でした。
それがすごく印象に残っていて、違いに釣り好きだからこそ、2人とも楽しそうなんですよね。
当時はあまり理解していませんでしたが、今となっては「釣具店の一つの大きな魅力」だと思えます。
誰かが笑うと、人が釣られて笑うということは多くの人が体験していると思います。
誰かが怒っていると、周りの人もピリピリしたり、怒り出したりすることも偶然ではありません。
必ず感情の共振は起きていると思います。
それを釣具店でやれば、楽しい場所になるに違いありません。
時には釣り仲間と談笑しながら釣具店を楽しむ方を沢山みてきましたから、釣具店で楽しむ方が来る場所であることを忘れないようにしたいものです。
最後までご覧いただきありがとうございます。