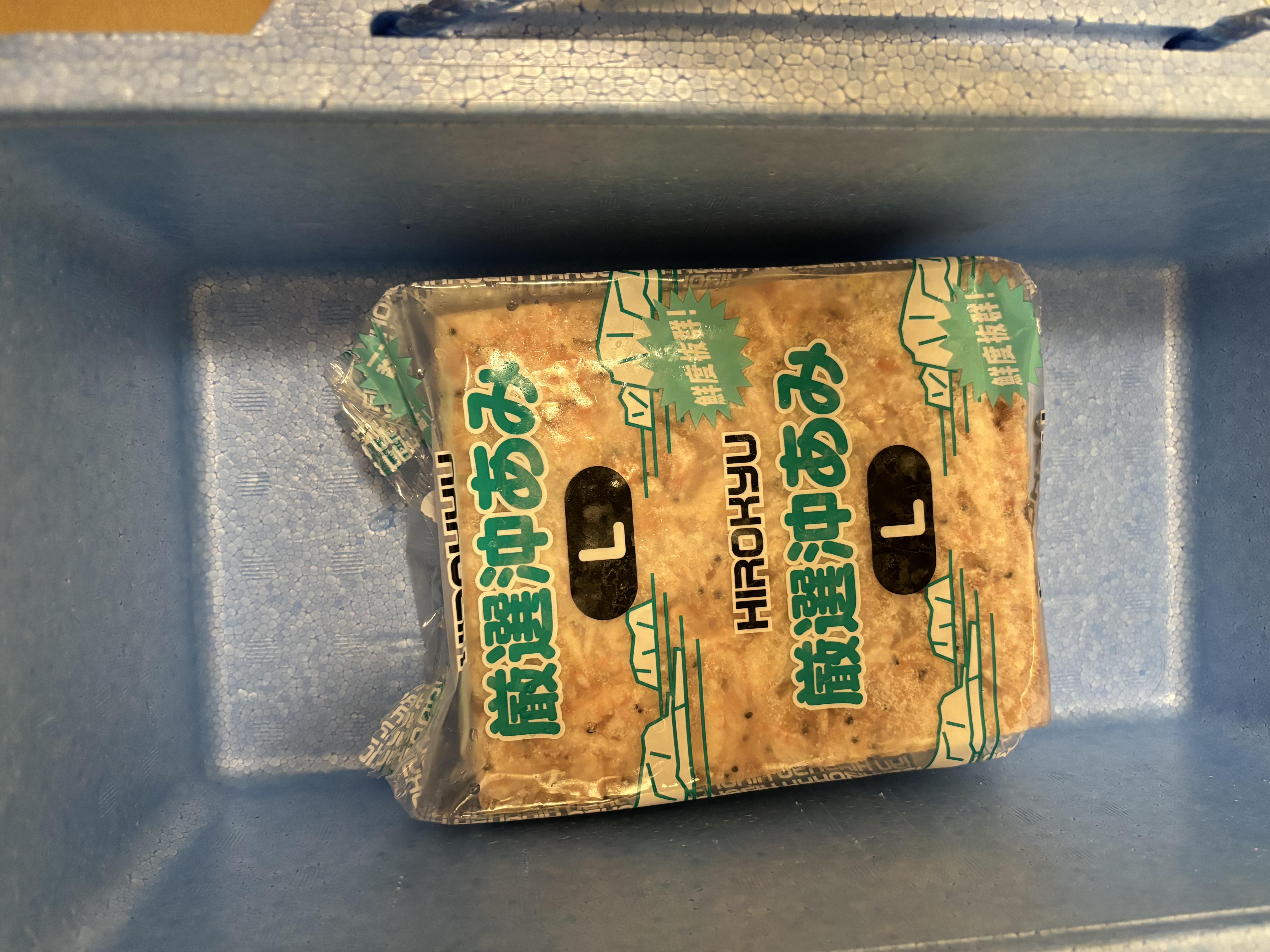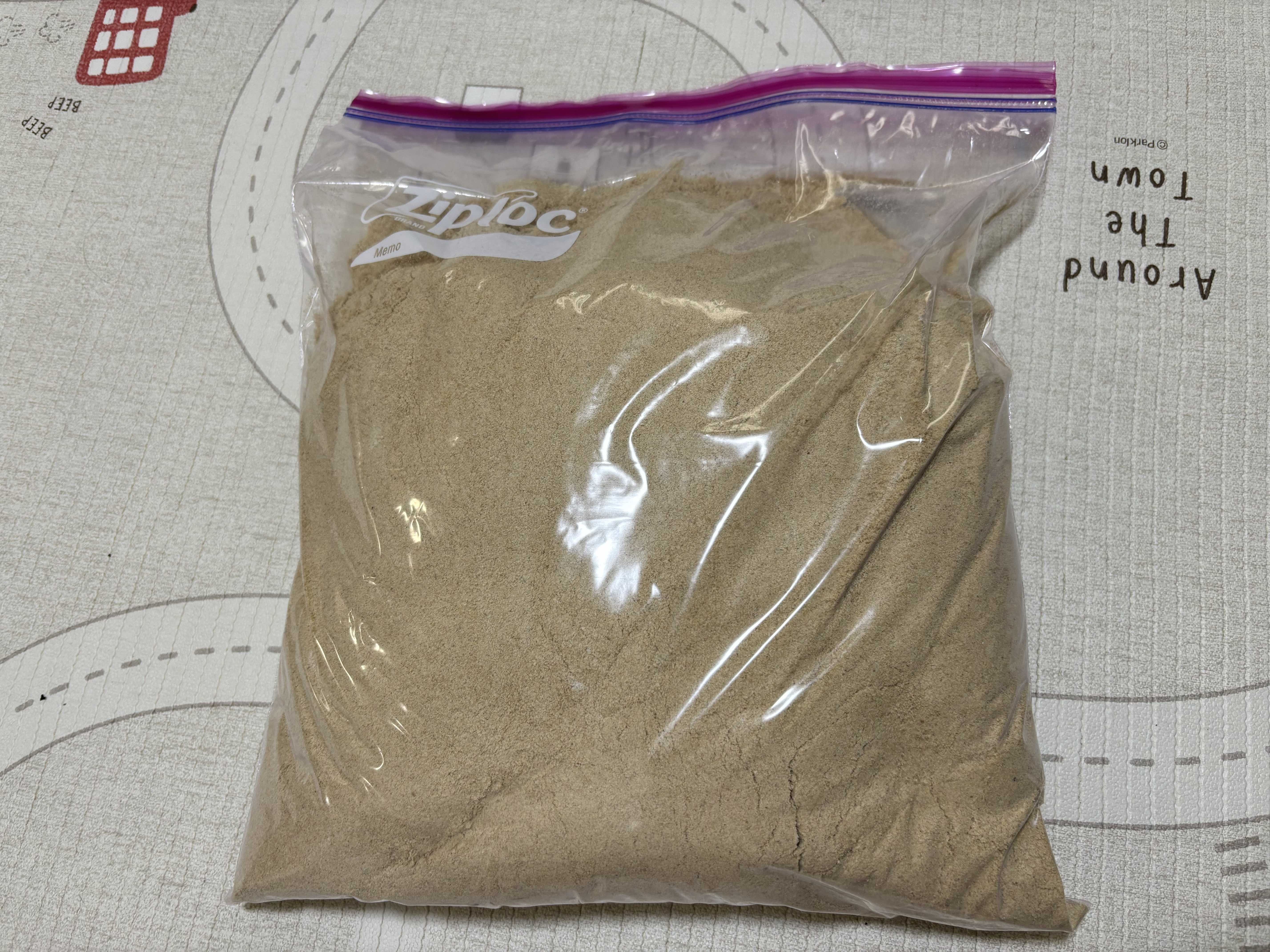名前のない磯に気軽にあがってはいけない理由

今回、船での渡船ではなく、山から移動する磯への注意点について説明していきます。
磯というフィールドはロマン溢れ、そして、釣人を最高の釣りへと導いてくれるとても、素晴らしい釣り場ではありますが、注意しなければならないことがあります。
それは磯場の干潮差を理解しているかどうかです。
今回は干潮差を理解せずに、大失敗した自身の体験を交えて記事にします。
東北の磯での学んだこと
僕は生まれが東北ですので、特に三陸沖の磯や牡鹿半島という根魚のメッカを中心に磯釣りを楽しんできた経験があります。
その際に東北の磯釣りをする中で感じたことは、自然の中に入る以上、色々な危険が身に迫るということです。
まず、磯におりるためにはそれなりの装備が必要です。
磯靴はもちろん、できる限り、両手はフリーになるように軽量な釣具類に、フローティングベストを着て、山をくだったり、登ったりします。
人によってはヘルメットをかぶって磯歩きをする人もいます。
磯におりるためには、山を歩く必要があることが多く、木や草の上を歩いていくので、知らないうちに、見たことのない虫が体にくっついていたことや蚊などの大群に囲まれていたこと、スズメバチの巣が近くにあり、危険な思いをしたことなど、色々体験しました。
そうした経験から自然の中でどんなことをが起きるわからないので、事前にある程度、山の知識を持っている人と同行した方が良いということ、そして、何かあった際の装備も必要ということです。
ここでは詳しくは話しませんが、何が起きるかわからないので、救急セットやポイズンリムーバー(血を抜くアイテム)、ライターなどは山に行く際は持っていきます。
そして、動物対策も必要な地域もあります。
熊や鹿、日本猿などがいる地域もあります。
東北の磯では、「鹿(シカ)」が大量にいる地域があるので、鹿に関する知識も必要です。
雄の発情期や子連れの母鹿など、襲ってくる可能性のある時期もあるので、やはり、山を知っている人や最低でも鹿の生態を調べてから入山するべきです。
また、磯におりてからも油断はできません。
三陸の磯はリアス 式海岸と言い、切り立った磯や磯と磯の間が狭く、しかも浅いため波が高くなりやすい傾向にあります。
そのため、多くの釣人が毎年のように波にさらわれる事故が発生しますが、一番の理由はそうした海沿いの地形から繰り出される高波を理解していないことに起因するのだと思います。
山歩きだけですでに体力を使い、ヘロヘロになりますので、磯におりたら、高いところで休憩もかねて海の観察をすることが大事です。
たまに大きな高波がくるような場所だった場合、その釣り場での釣りは中止すべきで、波が当たらない面や磯を移動した方が無難です。
時間帯によって高波が来る来ないもあるため、一概には言えませんが、最初の観察をするだけでも磯の高波の特性が理解できるので、必須の行動と言えると思います。
真鶴での恐怖体験
ここからが本題ですが、神奈川県に真鶴地域という都心部からアクセルの良い釣り場があります。
夏にはブリなどが回遊してきたり、ロックフィッシュはもちろん、沖での船釣りなど、今もなお魅力溢れるフィールドです。
そんな真鶴で、秋深まる時期に友人と2人で磯におりた時の話です。
比較的アクセルの良い磯から少し離れた場所から、獣道チックなところを通り、多くの釣人が歩いたであろう道を頼りに山をくだっていきました。
途中先人が作ったロープなどを利用しながら、おりていきます。
この時はフローティングベストに釣り道具やルアーを入れ、そして、リュックスタイルでリュックの横に竿をくくり付ける形で、グリップ付きの軍手で移動していました。
磯におりる装備としては、東北の経験もあり、十分でした。
結構、急な山道をくだりましたが、すでに磯には釣り人がちらほらおり、結構磯におりている釣り人が多い印象がありました。
その時はその磯周りで釣りする場合、特に何も問題はないと判断していました。
午後から釣りをして、夕まずめの一番良い時間帯に釣りをして帰る予定でした。
友人との協議で、釣り人がいない方の磯に渡ろうと言うことになり、真鶴の磯の中でも番号がない磯へと移動することになりました。
真鶴の磯は番号が付けられているところが多く、番号がある場所で基本的に釣りをする形になります。
しかし、友人と僕はそんなことも構わず、魚が居そうな釣り場に移動していきました。
釣果は最悪で魚のアタリが一回あったかないかのかなりの苦しい状況・・・
せっかくおりた磯で何とか釣果をあげたい僕らはついつい、粘りに粘って磯が暗くなり周りが見えなくなるまで釣りをしていました。
ライトを照らす時間帯まで熱中して釣りをしましたが結果何も釣れず・・・
諦めて夜の山道を帰ろうかと相談していた矢先、とても妙なことに気がつきました。
波の音がさっきより大きな気がしたのです。
嫌な予感がして、磯先端から大急ぎで、移動してきた磯を辿ると元来た道はすでに海になっていたのです・・・
恐怖と絶望の時間がはじまります。
このまま磯の先端の方で満潮を超えるまで待つか、それとも帰る道を探すかという判断に迫られましたが、すでに帰りたい気持ちが強く、帰れる道を探すことに・・
しかし、辺りを見渡しても帰る道などほぼなく、懐中電灯の先に写るのは山の方にある木々のざわめきだけでした。
友人と協議して「海水に浸かってでも戻ろう」と覚悟を決めて戻ることにしました。
磯を通って帰るのではなく、山側に少し進むととても普段は移動することができないような断崖絶壁の磯があり、そこを通ることにしました。
足の下数十センチ下は海水で、断崖絶壁の磯の壁を磯靴のグリップを信じながら、渡るしか方法はありませんでした。
足首はかなりのきつい角度になります。
足場のある磯に辿りつくまでに10メートルくらいは断崖絶壁の磯を歩くしかない、足を滑らせた瞬間そこは暗闇の海・・・
釣り人生の中で最も緊張し、最も怖い時間のはじまりです。
もう本気の覚悟を決め、一気に断崖絶壁の磯を急ぎ歩きで忍者のように友人と渡っていきます。
死ぬか生きるかの賭けです。
どちらかが落ちても、救助できないリスクもあり、色々な緊張感が体を走り抜けます。
友人が先行して駆け抜けます。
その後を僕が追うようにして進みました。
もうできると信じ切るしかありません。
本当にこういう時は「信じることが全てです」
信じた結果、断崖絶壁の忍者走りは成功し、難を逃れたのです。
その後、一般的に危険なはずの夜の山登りがあまりに軽く感じるほどの恐怖体験でした。
後から色々調べてわかったのですが、干満差により沈んでしまう磯がある場所には磯の名前は番号が付けられないということを知りました。
磯にわたる際は潮の満ち引きにより磯がどうなっていくのかを調べてから行くべきでしたし、何より先人たちがあえて名前を付けない磯には何かがあると思った方が良いという教訓になりました。
また、普段は磯に貝が付いてあったり、磯の色が変わっていると海水がきている証拠だとわかるのですが、全くその兆候がなく、まさか全て水没する磯だなんて見抜けなかったのです。
僕らのように恐怖体験をしないためにも磯にわたる際にはルアーや餌釣りに限らず、下調べは必要です。
というか、山下りをして磯におりる際は必ずその磯で経験したこともある方が望ましいですし、一番は渡船屋さんに磯渡しをしてもらうことが最も確実に安全に磯を楽しむコツだと思います。
最後までご覧いただきありがとうございます。