クロダイ(チヌ)の基本的な生態・釣りの魅力と特徴『長編徹底解説!』

釣りのターゲットにしている魚の生態(生き方)のヒントをご紹介致します。
今回は、クロダイ(チヌ)を狙う上で、初めて釣りのターゲットにしてみる人、クロダイ(チヌ)を普段から狙っている人、どちらの方が見てもヒントがたくさん見つかるような記事にしてみました。
クロダイ(チヌ)という魚は雑食性のため、色々な物を食べます。
人間が食べるタンパク質なら何でも食べるんじゃないかというくらい何でも口にする魚です。
他、好奇心も旺盛で、色々な釣り方や餌で釣れたり、ルアーで狙うことが出来たり、釣人を飽きさせない奥行きのある好敵手です。
そんな僕も大好きなクロダイ(チヌ)について語り尽くしたいと思います。
黒銀とエメラルドの魚

僕が感じる・見えるクロダイ(チヌ)の姿は、時折、黒くカッコよく、時折、エメラルドに光り、時折、燻銀に輝く、そんな見方が逐一変わるような素敵な魚にみえています。
よく観察すると胸びれ周辺なんかも黒ではなく、青く輝いているのです。

銀色に輝くその魚が水面に上がってきた時の美しさは、釣人のテンションを一気に頂点へ持っていきます。
綺麗で美しい魚は沢山いますし、魚の個性が違えば、全く見え方が違います。
その中でも一際、目立つこの「銀色のヤツ」は多くの釣人を古くから虜にしてきたと感じざるを得ません。
この美しさは個体や釣れる場所によっても違いますが、実際に目の前で見ないとその美しさは伝わりません。
加工され、調光された画像を幾ら見ても、この魚の本当の美しさは釣人だけが体験できるものだと信じています。
特に白銀の色が強い個体はどちらかと言えば、濁りが強いエリアか深場に住んでおり、日焼けしていない傾向にあります。
黒くなりやすい個体は浅瀬や防波堤の際を泳いでいる太陽光で日焼けしている個体が多いように感じます。
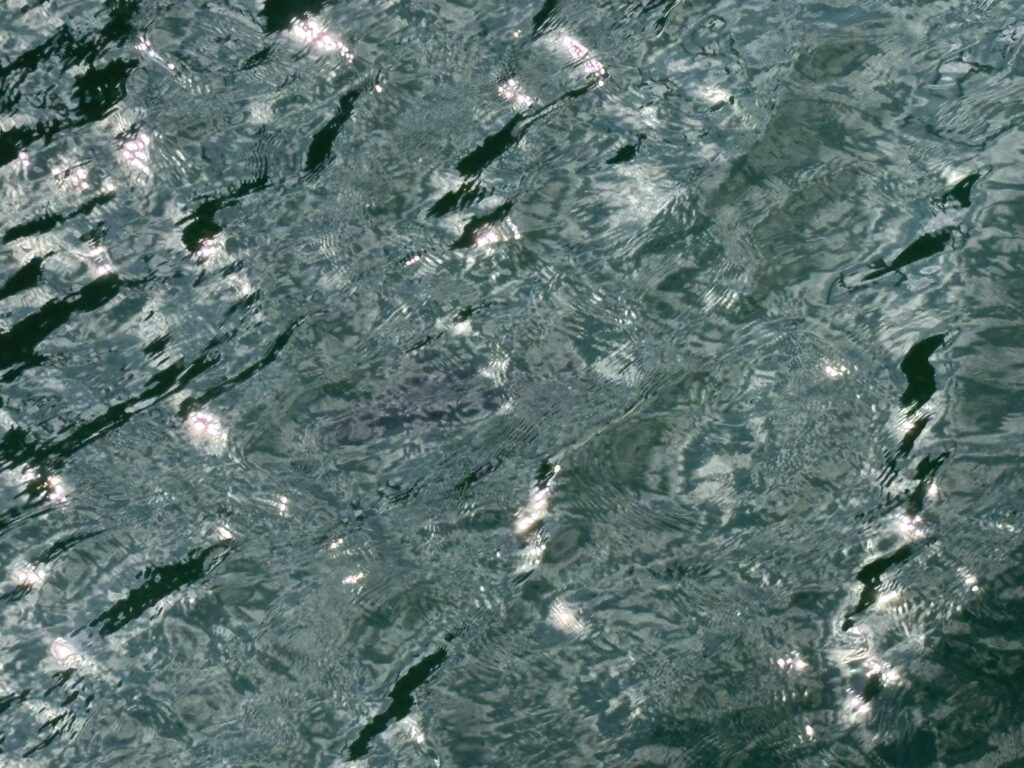
少し、水温が高い時期には水面付近を悠々と泳いでいるシーンは各地で見られる光景です。
カメラ越しだとかなり見にくいですが。
つまり、よく汽水湖や気温の高い時期は浮いていることが多いのですが、実は水面付近まで浮いていることが多い魚でもあります。
フカセ釣りの2大ターゲット「メジナ(グレ)」と「クロダイ(チヌ)」の比較

○メジナ(グレ)

○クロダイ(チヌ) 「標準英名:black sea bream」
このサイトでもメインに紹介している「ウキフカセ釣り」の2大ターゲットと言えば、メジナ(グレ)とクロダイ(チヌ)です。
この2大ターゲットが釣人を熱くさせ、ウキフカセ釣りを多いに盛り上げる要因となっております。
メジナ(グレ)についても1記事以上書ける奥行きのある魚で、釣人の心を熱くさせ、かつ飽きさせない素晴らしいターゲットです。
それに劣らないレベルで、釣人を魅了してやまないのがクロダイ(チヌ)という魚です。
この2種類の魚の釣り目線での大きな違いは潮の流れ方だと思っています。
メジナ(グレ)に比べ、クロダイ(チヌ)は流れがゆっくりで、沖にハリ出す(沖側に流れる)潮ではなく、足下から横方向にゆっくりと流れる潮を好む傾向があります。
具体的に言えば、比較的流れがゆっくりな湾内などがクロダイ(チヌ)釣り場になりやすい傾向があります。
そのため、釣り場でメジナ(グレ)が釣れる釣り場とクロダイ(チヌ)が釣れるポイントは違います。
そして、ポイントの傾向として大きく違うクロダイ(釣り)の特徴が底付近を狙うことが多い点です。
メジナ(グレ)は中層の釣りがメインです。
水深を綺麗に半分に割った前後くらいの水深を上下に移動するのに対して、クロダイ(チヌ)は水深関係なく、底付近で釣れやすい傾向になります。
底付近の砂地や岩礁帯に潜む甲殻類やエビ、その他、貝類などを好むため、捕食する場所自体が海底付近の魚です。
「クロダイ(チヌ)は底を釣れ」と言われる通り、難しいことを考えず、底付近に仕掛けのタナ(魚のいる層)を合わせる方が釣りやすい魚でもあります。
例えば、水深が7mだとすれば、仕掛けの針先が7mに到達するように調整するイメージです。
根がかり(海底に針・オモリや仕掛けが引っかかること)するようなら、少しづつ浮かしていけば良いのです。
ただし、クロダイ(チヌ)の遊泳している層と魚が口を使う層が違っていたりします。
つまり、浮いているクロダイ(チヌ)を底付近に寄せるという考え方で海底付近に棚を合わせるという考え方です。
もちろん、逆も然りです。
面白いことに釣人にとっては嬉しい話ですが、メジナ(グレ)とクロダイ(チヌ)は俯瞰した分布域でみると、重なっていることが多いです。
つまり、同じ釣り場でメジナ(グレ)やクロダイ(チヌ)が一緒に釣れることも多いにあり得るということです。
釣り場にもよりますが、狙い方やポイントが少し違うだけということも大いにしてあるのです。
ですので、分布域は一緒でもそれぞれ、同じ海の中では棲み分けがあるということです。
クロダイ(チヌ)のいろは

釣り時期と産卵行動
基本的に通年釣れます。
場所によって、冬は少しお休み期間が続きますが、時間をかけてじっくり狙えば、真冬でもチャンスはゼロではないです。
産卵時期は春で、2月〜5月にはお腹の大きなメスが釣れます。
この産卵前の餌を捕食して回遊したり、産卵の準備期間を「のっこみ」と表現します。
海水温の目安としては16〜20℃くらいで、産卵が始まると20℃は超えていることが多いです。
この時期はあくまで産卵の回遊がメインで、放卵している時期とは異なりますが、お腹が大きくなっているので、産卵期のメスを見かけることが多い時期です。
地域により違いますが、4月〜6月に産卵をする個体が多く見られます。
産卵期のメスは1ヶ月にわたり、卵を産み続け、詳細はその名の通り闇の中ですが、闇夜に散乱行動を行っているものと考えられています。
体重1キロの個体で、1ヶ月に200万個以上の卵を放卵すると言われており、相当な量の卵を放卵しているため、この時期のクロダイ(チヌ)は特に栄養を欲していると考えれます。
そのため、呆気なくメスのクロダイ(チヌ)が沢山釣れる時期でもあります。
その他、この時期特有の食い渋りや食い気のばらつきなどは、人間と一緒で産む前の精神的な側面であったり、ツワリに相当する身体的な負荷が魚にも生じていると考えれば、釣り人が経験する釣りの難しさが合致する気がします。
やや無理やりですが、人間もクロダイ(チヌ)も産むことやその前後は同じようなものだと感じてしまいます。

写真はおそらく、放卵する時期の前の「のっこみ」時期のメスの個体の卵
放卵中は透明な卵がみえたり、色が濃くなったりするようです。

上のメスの個体と同時に釣れたオスの個体の白子
形態的特徴
僕の住む関東では出世魚的に「チンチン」→「カイズ」→「クロダイ」と呼ばれますが、最近ではその呼び方もほとんど聞かなくなってきました。

基本的に黒い帯のような縦線が数本入り、腹びれ、尾びれともに黒灰色系の色をしています。
エメラルドや青く光ってみえることも多く、目にはアイシャドーをしているような個体もあります。
他、頭でっかちな個体から体がスリムで細長い個体、餌を鱈ふく食べてラグビーボールのようになっている個体と、地域や魚の個体によって個性が違います。
腹びれや尾びれが黄色の「キビレ」という種類もいますが、クロダイ(チヌ)とは種類が違います。
○キビレ
クロダイを狙っているとたまに釣れてしまう魚で、生息域はほぼ一緒ですが、クロダイ(チヌ)が連発する時は基本的に姿を現さない謎の魚。
基本的な習性
クロダイ(チヌ)は基本的には北海道より南の沿岸地域に広く分布している魚です。
ほぼ、どの海にも生息していると言っても良いほど、幅広く生息しています。
汽水域(海水と淡水が混じっている水域)や磯などの岩礁帯、防波堤周りなど、とにかく潮が早すぎない浅瀬に生息していることが多いです。
クロダイ(チヌ)は生まれてから3〜4年はオスとして成熟し、その後はメスに性転換するという習性を持っています。
そのため、男性陣には嬉しい?のか、大きなクロダイ(チヌ)はみんなメスです。
色々な魚と混在して生息していますが、同じ捕食レベルの魚と比較した時、キジハタの生息域とかなりかぶっています。
主に、防波堤周りの水深の変化する箇所、船道(チャネル)、防波堤のケーソンなどの基礎周り、捨て石周り、消波ブロック周りなど、障害物がある場所を好みます。
この辺りのイメージとして、ロックフィッシュと呼ばれる岩礁地帯に生息している魚に近しい場所に住んでいます。
ただ、同じポイントに混在していても、ロックフィッシュのように岩の中や隙間に隠れているというよりは、同じエリアをぐるぐるを回遊していたりすることが多いです。
そのため、同じポイントに仕掛けを投入し続けても、クロダイ(チヌ)が回遊してくれば、いきなり連発するなんてこともあります。
潮が早すぎない地形変化周りを回遊している傾向があり、それを解き明かすと魚釣りが相当楽になります。
例えば、釣りをしていて実際によくあるシチュエーションがウキの横移動のスピードが遅くなる(=つまり潮の流れが緩くなる瞬間)時に連発して、潮が早くなるとアタリが遠のくことが多々あります。
ですので、そもそも潮の流れが早くなるような防波堤先端や地形上細くなって急流な流れが生じるポイントはクロダイ(チヌ)が釣れにくい傾向にあります。
経験上、潮の流れのタイミングは緩くなった瞬間にアタリが連続することが多いです。
悪食として言われることが多いクロダイで、色々なものを捕食しています。
貝類はもちろん、砂地にいる虫、魚類、甲殻類全般、そして、釣り餌で驚きなのはみかんやスイカなんかも食べます。
餌として認識したら、色々なものを捕食しやすい性格のようですが、好みの食べ物を見つけたら、偏食して食べることもあるので、なんでもかんでも口にするという訳でもありません。
フカセ釣りの際にクロダイ(チヌ)釣りの際にはコーンや団子餌、練り餌、オキアミ、サナギなど、偏食している時に備えて、色々持っていくのもクロダイ(チヌ)釣りならではの光景です。
フカセ釣りの撒き餌にもよく反応するクロダイ(チヌ)ですが、意外にも嗅覚に優れていることが研究でわかっています。
海中でのニオイ物質を感知する繊毛と呼ばれるものが密集している嗅坂数が55〜60ほどあり、メジナが25程度のため、クロダイ(チヌ)はニオイに対する感度が良いと判断できます。
そのため、クロダイ(チヌ)がいるポイントに対して、撒き餌をまっすぐ落とすよりも、やや潮上(潮が流れてくる上流側)に投入し、撒き餌のニオイで魚を寄せることができるのです。
クロダイ(チヌ)は基本的に群れで泳ぐ魚ですが、大型になればなるほど、単独で生活しているようです。
また、目的を持って回遊している個体も多く、一定のテリトリー内(例えば、手前の岬から次の岬まで)をぐるぐると回遊しているような動きを示す個体が多いと言います。
餌や自分が心地よい潮の流れ(早すぎる潮を嫌う)を求めて、回遊しているのではないでしょうか。
そのため、釣り場によっては、撒き餌を投入してもクロダイ(チヌ)の気配すら感じなかったのに、突然、バタバタと釣れ出すということがありますがそれは回遊している魚に当たっているということかもしれません。
この回遊のパターンを解読するレベルまで釣り込めば、クロダイ(チヌ)釣りの名人級に近い実力を出せるかもしれません。
また、回遊というと大きな移動があると感じますが、そうではなく、自分が好きなポイント周りにぼけーと浮いていたと思えば、気が向いたら、中層に浮いたりしたり、と行動に規則性がない個体もいるため、魚1匹1匹に個性があると言わざるを得ないと思います。
回遊個体や居つき個体と呼ばれる魚には、色や体型の違いなども見受けられることもありますので、魚の見た目でどのような動きをしているのか判断することも長年釣りをしていたら可能になるはずです。
ただ、魚が移動する大きな要因は水温ではないでしょうか。
変温動物である魚は水温が高くなればなるほど、適温に近ければ近いほど、元気に移動できます。
真冬などの水温がかなり下がってしまう時期はあまり動かずに底付近でじっとしていることが多いと聞きます。
大学の実験ではタグ付きのクロダイ(チヌ)が2日間に83キロ移動した研究もされているようで、完全な生態の解明にはまだまだ時間がかかるのかもしれません。
クロダイ(チヌ)は黄色がお好き?

クロダイ(チヌ)は色盲説がよく言われています。
ようは色がほぼ認識しておらず、色のコントラストなどで判断しているという見解です。
しかし、実際には実験室で色が見えているかの実験に成功していないと言われており、いまだにはっきりしたことはわかっていません。
ただ、昔から釣人の多くは「コーン」や黄色の撒き餌など、黄色に対するクロダイ(チヌ)の反応が非常に良いことを知っています。
そのため、オキアミを黄色く染めたものやそもそも色が黄色のコーンなどを用いられるのです。
となると、見えにくい色、見やすい色はあれど、色を識別して、さらに好みもあるということがほのかにわかってきます。
信じるか信じないかはあなた次第ですが、クロダイ(チヌ)に黄色の餌は鉄板であり、特効餌であると考えられています。
クロダイ(チヌ)釣りで釣果をあげるためのヒント
多種多様なクロダイ(チヌ)釣り
クロダイ(チヌ)釣りには色々な方法があります。
僕が住んでいる横浜市ですと、大人気な釣りが落とし込み釣りです。
貝や小さな蟹を付けた針にガン玉を打ち、それを防波堤などの際に落とし込んでいき、糸が止まった瞬間にダイナミックな合わせをいれる釣り方の一つです。
他にも棒ウキを使った底に針を這わせた状態で、オキアミやサナギ、コーンなどの餌を使うフカセ釣り、または円錐ウキを使って中層付近にオキアミを漂わせて釣るフカセ釣りです。

底付近でクロダイ(チヌ)を釣る場合、コーンやサナギ餌などが有効です。
(画像はさなぎとコーンを混ぜてミンチ状にしたものです)
中層の釣りを散々試しましたが、コーンやサナギはやや効果が薄いため、中層の釣りをするのにはオキアミがやはり適していると感じます。
ねり餌系もどちらかと言えば、底付近を狙う釣りに適しています。
また、コーンやサナギと言った餌はなぜか他の魚は食べたがりません。
そのため、クロダイ(チヌ)をピンポイントで狙う時の特効餌となるのです。

撒き餌にはさなぎ粉を混ぜるとクロダイ(チヌ)に対して集魚効果が高まります。
その他にもカカリ釣りと言われるイカダや船から団子の中に刺し餌を隠して投入し、団子が崩れた後に刺し餌を食わせる釣りがあります。
最後に「チニング」と呼ばれるルアーでクロダイ(チヌ)を狙う方法があります。
表層をトップウォーターと呼ばれるルアーで水しぶきをあげて、活性をあげて口を使わせたり、反対にワームを使って底付近をずるずるとズル引きして釣る方法もあります。
ユムシなどを用いて、投げ釣りでクロダイ(チヌ)を釣る方法もあり、このように地域によってその釣り方は千差万別。
多種多様な釣り方がある多様性のある釣りを楽しめる素晴らしいターゲットであると言えます。
最後にルアーでも餌釣りでも色々な釣り方でこの魚を釣ってきた所感として、口の感度がとても良い魚であると感じています。
ルアー(ソフトルアー)を長く噛んでいることはほとんどなく、基本的にルアー釣りの場合は即合わせでヒットします。
むしろ、ゆっくり食わせて合わせるなんて釣り方がほぼ存在しないことを存在すると、口の中の違和感を感じやすい魚であることは間違いなく、口の感度が高いと言わざるを得ません。
ウキフカセ釣りにしても、ウキが沈んだと思ったら、すぐに口から餌を吐き出しているように感じることも多く、口の感度は他の魚に比べて高いように思います。
クロダイ(チヌ)を狙うための「ポイント」こそ、本質
僕は小学生の頃から色々な魚釣りを楽しんできて、ルアーフィッシングに長くハマり、色々なターゲットを狙ってきました。
その中で得た最大の知見は「釣り場のポイント」の重要性です。
ポイントが合っていれば、後はタイミング次第、そして、仕掛けを外していなければ釣れます。
反対にポイントを大きく外していると、いくら待っても何をしても釣れません。
例えば、この防波堤でクロダイ(チヌ)が釣れている情報があると言われて、現地に言っても釣れないことが多々あります。
やはり、常連さんやポイントを理解している人が数を釣っているだけというケースが多く、いきなりはじめての釣り場に行き、釣果をあげるのは難しいことも少なくないです。
クロダイ(チヌ)釣りに限らず、どの魚でも外せないポイントの特性があります。
クロダイ(チヌ)で言えば、「地形変化」です。
特に沈み込んでいるややこしい岩などの岩礁帯や藻場などは、クロダイ(チヌ)の回遊ルートの目安になっていることが多く、視覚的に判断しながら、回遊していると考えています。
特に硬い底質のポイントには自然と餌になる生物も集まってきます。
そのため、かけ下がり、かけ上がり(ブレイク)と呼ばれるところで、魚のアタリが集中することが多いです。
かけ下りやかけ上がり(ブレイク)といった地形変化は大型魚にとっては餌場(食事場)になっており、小魚や甲殻類にとっては食べられる危険地帯となることが多いのです。
ウキフカセ釣りだけをしていると、海底付近がどのような地形になっているのか、何が沈んでいるのか、どのような底質なのか、わかりにくいことが多いです。
ルアーをやってきた僕にとって、それらをルアーでズル引きして探ることはよくやっていたので、ポイントを探すことは得意なことでしたが、ウキフカセ釣りをしてから、ポイントをダイレクトに探すすべがなくなってしまいました。
せいぜい、ウキがこの辺りでは上下にぷかぷかしやすいから、岩などが張り出しているのではないかと予想するくらいでしかありません。
先ほど紹介した常連さんや釣り場でよく釣る人はこのような地形変化を中心としたポイントを見つけている、もしくは見つけるのが上手な人が魚をよく釣る傾向にあると考えています。
さらに、あまり教えたくない情報として、地形変化+水草・海藻が生えているエリアはクロダイ(チヌ)はかなりの確率で回遊してきます。
特に、春先に地形変化+水草・海藻が生え始めるポイントは大型のクロダイ(チヌ)やその他の魚もコンタクトしてくる重要なポイントになりやすいです。
そうした場所を秋や冬に見かけたら、覚えておくことが大事です。
また、こうしたポイントにはロックフィッシュ系(キジハタなど)とポイントがかぶることがあり、キジハタがいるところにクロダイ(チヌ)ありみたいなイメージもあります。
撒き餌をいくら撒いてもクロダイ(チヌ)の回遊ルート内に撒き餌が届かなければ、全く意味がないのと一緒で、このポイントを見極めることが釣り場での最重要課題であると言えます。

僕は餌釣り師としてズルしているかもしれませんが、はじめての釣り場では一通り、ウキフカセ釣りをいきなりはじめずに、「テキサスリグ」と呼ばれるワームにオモリ(シンカー)を付けたルアーで底付近の状況を探ってから釣りをします。
そうすることで、全体の地形的な状況を理解するに役立つのです。
僕のように特殊なやり方として、最初にルアーで釣り場をサーチするのも大変ですので、普通に餌釣りする場合は同じフィールドに通い続け、ポイントを見つけるまでトライ&エラーを繰り返すしかありません。
その釣り場で、よく釣る常連さんが陣取っているポイントをよく見ておくことも重要です。
そこには何かがある可能性が高いからです。
流れの速さを見極める
クロダイ(チヌ)は力強い泳ぎをする魚ではありますが、青物のように強烈な遊泳力がある魚ではありません。
そのため、防波堤や磯において、流れが早すぎるタイミングや場所では釣れない傾向にあります。
例えば、外洋に面した防波堤の端っこで最も流れが強く、流れの変化が激しいような場所はポイントにすらならないこともあります。
そのため、ある程度の潮の流れがベストで、何もわからない場合は内湾向きで釣りをスタートさせるのがベターだと考えます。
また、これも場所によって全く違ってきますが、普段から流れがある程度流れている河川の河口付近では、流れが緩くなったタイミングや反転流が発生しているポイントが良い時もあります。
いずれにして、クロダイ(チヌ)が好む流れがの適度な速さというものが存在するということを知るだけでも大きく魚に近く一歩になると思います。
むしろ、潮の流れが最も緩い筋が一番のポイントになり得ることも多くあり、クロダイ(チヌ)が好む流れの緩さは確実に存在しています。
地磯や沖磯などで、さっきまで同じポイントで青物が釣れていたのに、潮がゆっくりになったらクロダイ(チヌ)やロックフィッシュが釣れ始めたなんてことも一度や二度ではありません。
つまり、その魚種が好きな潮に乗って移動してくるのです。
ただ、横浜でよくあるシチュエーションですが、真夏となり「照りゴチ」として有名なマゴチが釣れ始める頃は、海がとても茶色くなります。
プランクトンの死骸や入れ替わりが激しく、赤潮チックになってしまっており、酸素が水中に足りていない状態となります。
そういう時は、流れが最もはやくなり、潮の入れ替わりが激しく、水が動く時にアタリが集中したりしますから、釣りとはこれが正解!とは言えない難しいものだと思い知らされます。
釣り場釣り場でのケースバイケースである点は忘れないようにしたいものです。
年なし(50センチアップ)への挑戦
クロダイ(チヌ)を餌釣りで狙う際に「年なし(としなし・ねんねし)」と言われる個体がます。
それは50センチを超える個体のことを言います。
60センチ越え、記録級の70センチも年なしの部類に入るでしょう。

僕は自慢ではありませんが、色々な魚のマックス級の魚を釣ってきています。
その中でも、特にクロダイ(チヌ)は50センチを超えると老成魚(ろうせいぎょ)としての風格を感じます。
顔つきがもう、40センチ前後のクロダイ(チヌ)とは明らかに違います。
生きた老成魚を釣りあげた釣り人だけが体感できる貴重な瞬間ですが、この長年生き延びたという堂々たる風格とオーラは魚に対する敬意を表したいとすら感じさせます。
基本的にクロダイ(チヌ)のみならず、魚は餌がある限り、無限に大きくなり続けるという特性を持っていますので、人と違い、身体的に成長し続ける生き物です。
そんな大型のクロダイ(チヌ)は長い経験やその習性から、大きくなればなるほど、釣れにくくなっていきます。
単純に個体数が少なくなることも要因の一つですが、釣人の仕掛けや餌、ルアーに対して、警戒心を持ち、軽はずみに口を使ってこないのが、大型魚の特徴です。
また、大型魚になればなるほど、一定のルーティンをして生活している研究もあり、いつも捕食している餌や捕食ポイント以外では口を使わないという点も大型魚を釣る上で難しくさせている要因と言えます。
大型を狙う釣人にとって、大きなヒントとなるのは、成魚になり、成長した個体ほど、磯場を好むという点です。
大型のクロダイ(チヌ)が磯場から釣れやすいというのにも、餌の豊富さなどが影響していると考えられます。
クロダイの年齢査定
大学の研究で、クロダイ(チヌ)の鱗から魚の年齢を調べようという動きが昔から行われています。
あくまで理論値である点は考慮するとして、50センチを超えると年齢的には13歳から19歳であることが多いようです。
餌が豊富な外洋などは大きくなっても年齢は若く、内湾や防波堤周りは年齢が高いという研究結果が出ています。
つまり、成長速度は環境にある程度依存する可能性が高いということです。
クロダイ(チヌ)は1匹1匹で個性が違う

僕が思う魚釣りの中で、魚1匹1匹にも個性があると感じています。
クロダイ(チヌ)という1種類の魚としてもくくりで考えてしまうと、本質を見失うことがあります。
やはり、魚1匹1匹に個性があり、臆病な性格をした魚を釣るのと、アグレッシブな性格をした魚を釣るのとでは、色々と違ってきます。
同じクロダイ(チヌ)でも何かが違う。
これこそが魚の種類は一緒でも個性がそれぞれ違うということなんだと日々感じています。
これって人間の世界でも変わりませんよね。
僕は魚釣りに対して思うことは、1匹1匹に対して、日々感謝の気持ちと尊敬の気持ちは忘れないように釣りを楽しみたいということです。
食べる魚もリリースする魚も一緒です。
よく居つきのクロダイ(チヌ)、回遊型のクロダイ(チヌ)とわかれているという話もありますが、それは正確ではないと思っています。
結果的に回遊することになったクロダイ(チヌ)もその場所が好きで離れない居ついているように見えるクロダイ(チヌ)も結局は人間と一緒で、生き方の違いでしかないと思います。
居ついていたい個体はどこに行っても居ついているでしょうし、回遊して動いてないと気が済まない個体もいます。
群れで一緒にいないと不安な個体もいますし、周りが食べている餌が安全かどうか確かめてからでないと口を使わない個体もいます。
どの角度から魚を見ても、結局はその魚の個性次第であり、同じように見えるクロダイ(チヌ)も例外ではないのです。
クロダイ(チヌ)は良質な白身魚

クロダイ(チヌ)は釣りという側面に加えて、釣り上げた後も楽しみがある魚です。
真鯛にも劣らない素晴らしい白身魚だということです。
色々な料理がビールに合いますし、お父さんのつまみにも、お子様のおかずにも、何にでも化けます。
ちょっと油物が食べたい時は、唐揚げやフライはもちろん、さらっと鯛茶漬け丼、ベーシックにお刺身、ユッケ、鯛めし、クロダイ(チヌ)のなめろうなどなど、料理の種類は作りたい放題です。

お子様のいる家庭におすすめは「甘酢餡かけ」です。
皮付きの身で唐揚げを作って、中華料理で使われる甘酢あんをかけるだけです。
大型のクロダイ(チヌ)釣れて、どう料理しようか、と悩んだ時こそ試して欲しいです。
パプリカや玉ねぎなどの野菜も一緒に炒めれば一緒に野菜もタンパク質も摂れるし、お子様もバクバク食べる料理です。
あっ、あと子供が赤ちゃんの時の離乳食として、僕が釣ったクロダイ(チヌ)の白身茹でて、ほぐして子供に食べさせていましたね。
夏の暑い時期には冷やし鯛茶漬けもさっぱりして美味しいです。
薬味たっぷりで食べて欲しいです。
それに、タイの頭を使ったあら汁や味噌汁は絶品です。
良い個体を引き当てた時は、贅沢に頭だけで潮汁も美味しいですね。
潮汁が甘く感じるんですよね。
タイっていうお魚は。
本当、鱗を除いて、捨てるところありません。
そんな食べても美味しい、釣っても嬉しい素晴らしい魚なのです。

僕が好きなのは鯛茶漬けです。
刺身を白ごま入りの漬けタレに漬けておいて、丼ののせ、薬味を乗せて完成です。
簡単で手軽でうまい!
生卵があれば、天国行きです・・・・
一点、河口や汚れた川で釣れたクロダイ(チヌ)はボラと一緒で臭いがきついものがありますので、内臓を出して、血わた(背骨内側についた腎臓)をしっかり取り除いて洗った方が良いです。
しっかり血抜きして洗えば問題なく食べられますよ。
クロダイ(チヌ)との思い出
最後にクロダイ(チヌ)について、僕の個人的な思い出を語って、筆を閉じたいと思います。
大学生の頃、釣り仲間でもあり、サークルの先輩でもある釣り好きの先輩と夜通し、無人島(離島)に釣りをしにいった時の話です。
先輩が投げ釣りをメインでやっていたのに対して、僕はルアーを使って深夜にロックフィッシュを狙っていました。
先輩がユムシを用いた投げ釣りをして数時間が経過した頃、辺りは無人島特有の静けさで、静まり返っていました。
潮も潮止まりを迎え、時計の針は深夜2時。
先輩と温かい飲み物でも作ろうかと考え出したころ、先輩の投げ竿から物凄いドラグ音が鳴り響きます。
静かな海に響き渡るあの独特なクリック音は、静かな海には似合わず、不思議な気分にさせてくれたのを今でもよく覚えています。
先輩が「でかい!」と叫びながら、ドラブを締め込み、一生懸命魚とファイトしています。
潮止まりのわけわからない時間帯に突然のドラグ音に、一気に興奮気味の2人は、その魚体をみて驚きました。
超大型のクロダイ(チヌ)だったのです。
網ですくって、陸まであげた時、その風格から明らかに50センチをゆうに超えるサイズであるとわかります。
深夜の年なし。
先輩が子供のように大はしゃぎしていました。
その後、僕の竿もしなり、2匹のソイをゲットしました。
先輩が用意してくれたG社のストリンガーに大型のクロダイ(チヌ)と僕のソイ2匹をかけて、防波堤の際に丁寧に落としていきます。
そして、1時間ほど時間が経った時に事件がおきます。
防波堤のリングに結んでいたはずも紐が風に揺られています。
「あれっ?」と2人して覗き込んでみるとストリンガーに付いている紐が切れていました。
慌てて確認すると、ストリンガーに付けられた魚もろとも、海の中に消え、釣り上げたクロダイ(チヌ)はどこかに消えていきました。
コンサート周りに鋭利なものはありませんでしたから、コンサートに紐が擦れて切れてしまったのでしょうか。
ストリンガー付きで逃げた魚達は生きられないでしょう。
魚に申し訳ないことをしたと感じたと同時に、あの大型のクロダイ(チヌ)が暴れ回り、防波堤のコンクリートに紐が擦れ、切れてしまったという事実に驚きを隠せませんでした。
あの大型のクロダイ(チヌ)のパワーが相当なものであることを物語っています。
その後、僕たち2人の竿が曲がることはなく、無人島での深夜の騒動は幕を閉じました。
先輩が帰り際に「こんな仕打ちありかよぉ」と嘆いていたのを今でも忘れません。
その先輩は今では漁師になり、毎日念願の魚達と生活しているようです。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。










